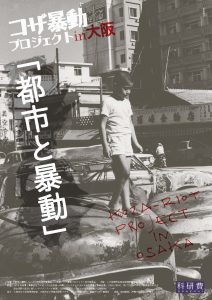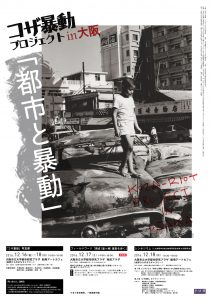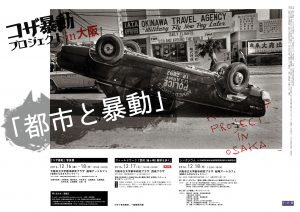山崎孝史
コザ暴動プロジェクト in 大阪 「都市と暴動」

開催趣旨
「コザ暴動プロジェクト」は、い わゆる「コザ暴動」を写した写真展を中心に、映画・ビデオ上映・シンポジウムなどの関連企画を展開する活動として2015年12月に沖縄市(コザ)で始まった。今回の大阪での開催は、2016年4月に明治大学で開催された「コザ暴動プロジェクトin東京」に続く、本土で2回目の企画である。
わゆる「コザ暴動」を写した写真展を中心に、映画・ビデオ上映・シンポジウムなどの関連企画を展開する活動として2015年12月に沖縄市(コザ)で始まった。今回の大阪での開催は、2016年4月に明治大学で開催された「コザ暴動プロジェクトin東京」に続く、本土で2回目の企画である。
「コザ暴動」は、まだ沖縄が米軍統治下にあった1970年12月20日未明、嘉手納基地前のコザ市で発生した。そのきっかけは米兵が起こした交通事故であった。当時、米兵による凶悪事件や性暴力は頻発しており、容疑者は罪に問われないことすらあった。こうした不条理に対する住民の怒りはうっ積しており、この夜ついに暴動という形で爆発した。群衆は事故現場周辺に駐車されていたMPや米人の車両を次々と横転させ、それに放火した。数千人の群衆は路上を二手に分かれ、放火・投石しながら、米軍および琉球警察と対峙した。
「コザ暴動プロジェクト」はこうした民衆の行動をあえて「暴動」と呼ぶ。それは怒れる民衆を「暴徒」とみなす危うさをはらんでいるが、異民族支配に忍従してきた沖縄の人々が「暴動」によって表現せざるを得なかった怒りの意味を、今の沖縄と日本で改めて問い直す必要がなかろうか。本企画の写真展とギャラリートークは、コザ暴動の「現場写真」の迫力とそれを撮影した写真家の肉声を通して、怒れる民衆の姿を大阪で再現する。
しかし、こうした「暴動」は沖縄でのみ起こったわけではない。本企画が開催される大阪では西成区の釜ヶ崎において日雇い労働者によって戦後24回もの「暴動」が発生している。戦前に目をやれば、首都東京でも1905年に日露戦争後の講和条約に反対する集会が大規模な「暴動」へと展開した「日比谷焼打ち事件」がある。本企画は「都市と暴動」をテーマとするシンポジウムにおいて、これら三都市で発生した「暴動」の歴史・地理的背景、展開過程、参加者属性、社会的意義を比較検討しつつ、なぜ都市は「暴動」を生み出し、なぜそれは今も語り継がれるべき出来事たりうるのかを考える。
なお、本企画の全てのイベントは一般に公開され、参加費は無料である。
開催内容
主催: 「都市と暴動」シンポジウム実行委員会(代表:山﨑孝史)
共催: コザ暴動プロジェクト実行委員会(代表:國吉和夫)、人文地理学会政治地理研究部会(代表:北川眞也)
協力: 大阪市立大学地理学教室、大阪市立大学都市研究プラザ、CR-ASSIST地域・研究アシスト事務所
後援: 琉球新報、沖縄タイムス、沖縄市、朝日新聞社
財源: JSPS科研費「軍事的圧力に抗う文化的実践―沖縄とパレスチナにおける地誌編纂と景観修復」(15K12954)、同「グローバル化の新局面における政治空間の変容と新しいガバナンスへの展望」(15H03277)(いずれも研究代表者:山﨑孝史)
チラシ(実物はA4判)・ポスター(B2判)は写真をクリックして下さい。
「コザ暴動」写真展
期日: 2016年12月16日(金)~18日(日)
時間: 午前10:00~午後6:00(入場無料、16日は午後7時まで開場延長します)
場所: 大阪市立大学都市研究プラザ 船場アートカフェ(辰野ひらのまちギャラリー)
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1丁目5-7 辰野平野町ビル地下1階
http://art-cafe.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/
出展写真家: 大城弘明、國吉和夫、平良孝七、比嘉豊光、比嘉康雄、松村久美、山城博明、吉岡 攻
関連展示品(沖縄市提供): 黄ナンバープレート、「騒乱罪粉砕市民集会」のチラシ、沖縄タイムス「コザ暴動」号外、「12・20反米騒動で弁務官に抗議」コザ市職労速報、琉球新報「コザ反米騒動 政治問題に発展」紙面、「被害を受けた車両・建物」の図
フィールドワーク「西成(釜ヶ崎)暴動を歩く」
期日: 2016年12月17日(土)
時間: 午後2:00~4:00
場所: 大阪市立大学都市研究プラザ 西成プラザ
〒557-0002 大阪市西成区太子1-4-3 太子中央ビル3F
http://www.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/satellite-office/fieldplazas/nishinari/
案内者: 山田實(NPO釜ヶ崎支援機構理事長)、水野阿修羅(釜ヶ崎地域史研究家)
内容: 戦後24回発生した西成(釜ヶ崎)暴動に関する現場レクチャーと釜ヶ崎フィールドワーク
申し込み: 参加者上限は30名程度。希望者が多い場合は抽選します。12月10日(必着)までに下記連絡先に電子メールか(電話返信先を記した)葉書でお申し込みください。落選者には12日までに連絡します。申し込みは締め切りました。
連絡先: 山﨑孝史
yamataka[at]lit.osaka-cu.ac.jp ([at]は@に変えて下さい)
〒558-8585 大阪市住吉区杉本3-3-138 大阪市立大学大学院文学研究科
シンポジウム(人文地理学会政治地理研究部会第20回研究会)
期日: 2016年12月18日(日)
時間: 午後1:30~6:00
場所: 大阪市立大学都市研究プラザ 船場アートカフェ (辰野ひらのまちギャラリー)
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1丁目5-7 辰野平野町ビル地下1階
http://art-cafe.ur-plaza.osaka-cu.ac.jp/
第1部 シンポジウム「都市と暴動―都市はいかに暴動を生み出したか」
パネラー
山田實(NPO釜ヶ崎支援機構理事長)「転換点としての90年西成(釜ヶ崎)暴動」
藤野裕子(東京女子大学准教授)「戦前東京の暴動と労働者文化」
山崎孝史(大阪市立大学教授、進行役)「基地の街コザと暴動を語る論理」
第2部 「コザ暴動」ギャラリートーク
パネラー
國吉和夫(写真家、元琉球新報記者)
小橋川共男(写真家)
比嘉豊光(写真家、雑誌編集者)
松村久美(写真家)
古堅宗光(元NPOコザまち社中幹事)
恩河 尚(沖縄国際大学非常勤、コメンテーター)
今 郁義(コザ暴動プロジェクト実行委員会、進行役)
「都市と暴動」シンポジウム実行委員会
委員長 山崎孝史(大阪市立大学教授)
副委員長 國吉和夫(コザ暴動プロジェクト実行委員会代表)
副委員長 北川眞也(三重大学准教授、人文地理学会政治地理研究部会代表世話人)
委員 今 郁義(コザ暴動プロジェクト実行委員会)
委員 秋友一司(ギャラリー・ラファイエット)
委員 今野泰三(大阪市立大学都市文化研究センター特別研究員)
展示協力 伊敷勝美(沖縄市役所)
支援スタッフ 青陰麻那(大阪市立大学学生)
支援スタッフ 大谷直樹(大阪市立大学学生)
支援スタッフ 鈴木まゆ(大阪市立大学学生)
支援スタッフ 千原佐和(大阪市立大学学生)
支援スタッフ 中西広大(大阪市立大学学生)
人間行動学概論IIの試験日程について
人間行動学概論II(前半部)の試験日程は11月25日ではなく18日です。お詫びして訂正いたします。
人間行動学概論IIの日程誤植について
ホームページと配布シラバスに人間行動学概論IIの第4週の日程(10月28日)が抜けておりました。10月28日は通常通り授業を行います。11月4日が学園祭のため休講となります。その振替は8日(火)となります。
新ホームページ開設
新しいホームページを開設しました。
後期が開講しました
現在後期開講科目についてのページの新設や更新を進めています。内容に関する質問などがございましたら「お問い合わせ」ページからお知らせください。できるだけ速やかに回答させていただきます。
2015年度博士論文・卒業論文
博士論文
今野 泰三(いまの たいぞう)
ヨルダン川西岸地区におけるイスラエル入植地と民族宗教派入植者に関する考察―死/死者の景観と規範共同体の境界
卒業論文
藤田 梨花(ふじた りか)
「大阪産(もん)」からみる都市近郊農産物の空間的広がり
卒業論文のテーマがなかなか絞れずに、テーマ設定だけに一年弱かかりました。 山崎先生にアドバイスをいただいて4回生になってからようやくテーマが決まった状態でした。 そのため、卒業論文のための調査期間、執筆期間ともに十分な時間がとれず、満足のいくまで調査は行えなかったというのが正直な感想です。 聞き取りの数を増やし、仮説を裏付けるだけのデータをもっと収集することができれば、また違う結果も出てきたのではないかと思います。最後になりましたが聞き取りにご協力いただいた方々、そしてアドバイスをしてくださった山崎先生、ご協力、ご指導いただき本当にありがとうございました。取りかかりが遅かった私が卒業論文をここまで完成することができたのは、皆様のご協力があったからだと思います。本当にありがとうございました。
私からの一言:当初から「食」への関心は一貫していましたが、論文のテーマが絞り込めなかった理由は、就活の内定時期のずれ込みや対象地域選定の遅れが影響したと思います。社会に出て物事に遅疑逡巡する時は、失敗を恐れず「えいやっ」と決めてかかってください。
2014年度卒業論文
奥野 寛央(おくの ひろひさ)
闘犬の観光化と衰退―闘う動物へのまなざしの功罪
テーマ設定を含めるとおよそ1年がかりの作業で頭を悩ませたことも多くありましたが、非常に楽しんで取り組みました。「闘犬」というテーマは早くに決まっていたのですが、テーマ自体が珍しく、先行研究が少ないので、難航が予想され最初は不安が多くありました。しかし、現地の方々や山崎先生をはじめとする地理学教室の先生方、院生や学部生の皆様のご協力で卒業論文を無事に完成させることができました。現地に赴き多くの話を聞いたことや多くの文献を読み卒業論文の方針を考えたこと等の卒業論文執筆の過程は私にとって価値のある経験となりました。協力して頂いた皆様へ心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。
私からの一言:地方の習俗を観光化させることが地方に外部のまなざしを持ち込み、習俗の存続が危ぶまれる事態をもたらすというパラドックスをテーマにした興味深い論考で、地方文化史としての価値もある論文となりました。このように問題設定ははっきりしていたのですが、素材をどう表現するかについていろいろ苦労もありましたね。言葉による表現力が試された論文でもありました。
御前 真琴(おんまえ まこと)
富山市八尾町の観光まちづくりにおけるアートプロジェクトとアーテイストの役割
卒業論文執筆にあたり、担当の山崎先生には、三年生の演習にはじまり、卒論提出まで、大変お世話になりました。何も決まっていない状態で担当をしていただき、調査地やテーマの決定から数多くの助言をいただきました。また、八尾町の「坂のまちアート in やつお」の実行委員会の皆様、そして出展アーティストの皆様には、急なお願いが多かったにも関わらず、快く受け入れていただきました。皆様のご協力なくては、卒業論文を書き上げることができませんでした。ひとりで何もわからない場所に滞在し、知らない人々の中に飛び込むという経験は初めてだったので、戸惑うことも困ることも多々ありましたが、今後の糧となる経験になったと思います。最後になりましたが、数多くの助言を下さった山崎先生、快く調査に協力してくださった八尾町の皆様、本当にありがとうございました。
私からの一言:とりあえず行ってみようという感じで調査を始めたわけですが、先行研究を踏まえた理論的枠組みに基づき、しっかりとした論述ができています。せっかくそうやって完成した成果ですので、あなたの経験談や論文を後輩が参照できればと思います。私はお手伝いしただけかもしれませんが、やはり卒論は一人で書けるものではありません。どんな仕事でも同じことが言えるかと思います。
2013年度卒業論文
岩神 幸平(いわがみ こうへい)
エルサレム旧市街における歴史的建造物の保全と住民生活支援
当初、漠然と世界遺産というテーマで卒論を書こうと考えていた僕は、山崎先生からエルサレム旧市街という提案をいただいた時、本当に可能なのかどうか半ば半信半疑で卒論に取り組み始めました。英語文献の講読から現地滞在の計画、インフォーマントの段取り、そして実際の調査に至るまで、山崎先生をはじめ、エルサレムで協力してくださった皆様のおかげで、困難を乗り越える事が出来ました。執筆に関しては反省点が残る部分が多々あり、少し悔いの残るものとなってしまいましたが、海外を対象に現地調査を行い、卒業論文を書きあげたというこの経験は、僕の人生の大きな財産となりました。ありがとうございました。
私からの一言:むりやりこちらからエルサレムに行ってもらおうとしたのですが、立派に調査を敢行されました。内容的にはもっと掘り下げられるテーマではありましたが、テーマ設定の困難性のみならず言葉や治安上の不安の問題も乗り越えた点で大変評価できる論文です。「世界中どこでも卒論を書こうと思えば書ける」という意気込みが後輩に伝わればと思います。
2012年度卒業論文
吉川 絢(よしかわ あや)
創造地区形成への取り組み―沖縄クリエイターズビレッジ事業を事例として
卒業論文執筆にあたり、山崎先生をはじめ調査地におけるインフォーマントの方々には本当に貴重な体験をさせていただきました。とくに現地での調査では、人と人とのつながりの中で生まれる力のようなものが感じられ、つい夢中になって長くお話を聞いてしまうこともありました。しかし調査地に行って聞き取りをさせていただく前、卒業論文を実際に書き始める前など、準備不十分で臨んだ作業や調査が多くありました。そうした不備により有効な調査や執筆ができず、ご協力いただいた各方面の方々にご迷惑をおかけすることとなってしまいました。今後は卒業論文に関する調査や取り組みでの反省を活かし、計画的な物事の進め方をしていきたいです。
私からの一言:コザという「基地の街」の再生について、ズーキンの「創造地区」という概念を用いて考察し、一週間という短い期間でしたが現地に入って丁寧に聞き取りをした成果です。私のフィールドでもあるので、色々サポートできたのですが、役に立ったかな。